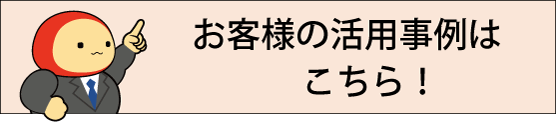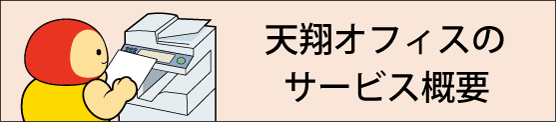宅建業はレンタルオフィスで開業できる?開業要件やメリットを解説
投稿日:2025年3月31日
更新日:2025年7月23日

初期費用が安く好立地で開業できるレンタルオフィスは、スタートアップなどが開業する際にも便利です。しかし、開業にあたってオフィスの要件が定められている宅建業の場合、レンタルオフィスを使用するには、個室の独立性や専用設備など、特定の要件を満たす必要があります。
この記事では、宅建業をレンタルオフィスで開業する際の条件や設備について解説します。開業を目指す方がスムーズに免許を取得し、安心して事業をスタートできるようポイントを押さえましょう。
目次
宅建業はレンタルオフィスで開業できる?
宅建業はレンタルオフィスを使って開業することが可能です。ただし、すべてのレンタルオフィスが宅建業に対応しているわけではありません。
宅建業をレンタルオフィスで開業するにあたっては、物理的にも社会的にも独立した空間であると証明でき、かつ賃貸借契約を結んでいることが必要です。
ただし、レンタルオフィスの運営会社が宅建業免許の細かな条件を十分理解していない場合もあります。そのため、運営会社だけでなく、各都道府県の宅地建物取引業免許(宅建免許)担当部署や専門家に開業可能か事前確認を取った上で契約することが大切です。
宅建業とは
宅建業(宅地建物取引業)とは、「宅地または建物の売買・交換」、「売買・交換または賃借の代理」、「売買・交換または賃借の媒介」を業務として行うことを指します。宅建業の代表例は、不動産の売買契約や仲介業務です。なお、建物や土地の賃貸業や物件の管理業務は宅建業には含まれません。
宅建業を営むためには、個人・法人を問わず、事務所の所在する都道府県の知事(複数の都道府県にまたがって営業する場合は国土交通大臣)より宅地建物取引業免許を取得する必要があります。
また、宅建業の開業にあたっては各事務所に1人以上専任の宅地建物取引士(宅建士)を配置しなければならないなど、さまざまな要件が定められています。
宅建業の開業申請ができるオフィスの要件
レンタルオフィスで宅建業を開業する場合は、「継続的に業務を行うことができる施設」という要件を満たす必要があります。
第一条の二 法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの
(引用:e-gov法令検索「宅地建物取引業法施行令」/ https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000383#Mp-At_1_2 引用日2025/3/13)
加えて事務所は法的には、「物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えている」ものと解釈されます。
(出典:東京都「宅地建物取引業の免許のあらまし」/ https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/juutakuseisaku/takken_menkyo02)
バーチャルオフィスやフリーアドレス形式のコワーキングスペースでは、「継続的に業務を行える、独立した施設」と認められないため、開業は不可能です。したがって、継続的に業務を行うことができる施設として客観的に認められるに足るレンタルオフィスを契約しなければなりません。
また、レンタルオフィスですでに宅建業を開業している事例があったとしても、オフィスの場所や契約内容によっては開業できないケースもあります。以下では、レンタルオフィスで宅建業を開業するのに必須となる各要件について解説します。
完全個室である
レンタルオフィスを利用して宅建業を開業する場合、事務所が完全個室であることが必須要件となります。
完全個室とは、他社と共有せず、自社専用の独立した入口を持ち、明確に仕切られた個別スペースのことです。
ワークスペースを共用するブース貸しや、仕切りが180センチ未満のスペース、扉のないオープンスペースでは申請が認められません。仕切りとなる壁や固定パーテーションは、簡単に動かせない構造であり、高さ180センチ以上であることが条件です。ただし、床から天井まで完全に塞ぐ必要はなく、180センチ以上の高さがあれば上部が空いていても問題ありません。
ガラスで区切られており、互いのオフィスの中が見えるタイプのレンタルオフィスの場合、事務所の中が見えないように180センチ以上の目隠しをする必要があります。目隠しはパーテーションである必要はなく、カーテンなどで顧客のプライバシーが十分に保護される環境であればOKです。
共用部のみを通ってオフィスに出入りできる
宅建業に必要な事務所の独立性を保つためには、自社の事務所スペースに他社の従業員や来客が立ち入ることがなく、来訪者が直接アクセスできる状態が求められます。
エレベーターや共用の通路を経由してオフィスに入ること自体は問題ありませんが、オフィスの出入口は他社と共有できません。同フロアに複数の法人が入居している場合は、それぞれの事務所に専用の入口があり、他法人のスペースを通ることなく、自社に来客が出入りできる動線を確保することが必要です。
レンタルオフィスの中には各事業所が利用できる共用のオフィススペースが存在するところもあります。共用部が休憩スペースであれば問題ない可能性が高い一方、業務が行える場合、「事務所スペースに他社の従業員や来客が立ち入れる状況」と解釈されるリスクがある点に注意しましょう。
社会通念上十分な広さが確保されている
宅建業の事務所には、「社会通念上、事務所として適切な広さを有している」ことが求められます。宅建業を行う代表者や宅地建物取引士が問題なく業務を行えるよう、従業員の人数分の執務スペースに加えて、対面で接客可能なスペースを個室内に確保しなければなりません。
代表者が専任の宅建士を兼任し、1人だけで宅建業を営む場合であっても、椅子と机が1つずつ置かれているだけでは足りません。自身が執務を行う机と椅子に加えて、さらに顧客との対面接客を行うための机と椅子が必要です。これらの設備を置けるだけの十分な広さが求められます。
また、共用スペースを接客用に利用するのは、事務所の独立性に反するため認められません。共用の会議室は複数の企業が利用するため、「自社専用のスペース」とはみなされないためです。
24時間365日自社社員のみが利用できる
「継続的に業務を行うことができる施設」という要件をクリアするためには、24時間365日、自社社員のみが独占的に利用できることが必須です。時間貸しや曜日ごとの利用制限があるレンタルオフィスでは、宅建業の開業を認められません。昼間は自社が利用できても、夜間や休日に他社が利用するような契約形態は、継続的に業務ができる事務所として基準を満たさないため不可となります。
レンタルオフィスを使って宅建業を開業する場合、運営側から「24時間365日利用可能である」という証明書や誓約書を発行してもらう必要があります。契約前に書類の発行に協力してもらえるか、担当者に必ず確認しましょう。
最低1年はレンタルできる
宅建業法上、事務所の位置が安定的かつ継続的であることが求められており、短期間の契約や3か月単位の自動更新といった契約形態では要件を満たせません。最低でも1年以上の長期間レンタルが可能なオフィスを選ぶ必要があります。
また、レンタルオフィスを使って宅建業を開業する場合、契約期間が明記された契約書の提出が求められるケースが一般的です。契約書の内容に不備や不明確な点がある場合、免許取得が認められません。
加えて、契約期間だけでなく、レンタルオフィスそのものが経営的に安定しているかどうかも重要です。宅建業は開業するオフィスに要件が多いこともあり、事務所の移転に際して他職種以上にコストや手間が発生します。
事業の継続性や安定性を考え、経営基盤がしっかりした信頼できるレンタルオフィス会社を選ぶようにしましょう。
宅建業をレンタルオフィスで行うときに必要な設備
宅建業の開業にあたっては、レンタルオフィスが事務所として認められるに足る設備を、開業前にそろえておく必要があります。開業までに設備が不ぞろいの場合は、開業を認められないケースもある点に注意しましょう。
●レンタルオフィスの開業に必須となる設備
| 項目 | 内容 |
事務所専用の固定電話 | 携帯電話や、自宅・他社との兼用ではなく、専用の固定電話回線が必要です。ただし、近年ではインターネット電話(IP電話)の利用も許可されるケースが多くなっています。 |
最低2人以上が執務・接客できる家具 | 執務を行うための机・椅子・収納などのオフィス用家具と、来客対応スペース用の家具を用意する必要があります。1人で開業する場合でも、自分と顧客で合わせて最低でも2人分のスペースが求められる点を押さえておきましょう。 |
宅建業務に必要なOA機器 | パソコン、プリンター、コピー機、シュレッダーなど、宅建業務で必要な書類作成・管理ができるOA機器が必要です。共有のOA機器が設置されている場合でも、共用スペースではなく事務所内に専用の設備が整っていることが求められます。 |
表札・郵便物受け取り用のポスト | 登記簿謄本通りの社名を記載した表札と、事務所名を明記した自社専用のポストが必要です。 |
免許申請にあたっては、各設備が整っていると証明できる形で室内の写真を撮影し、申請書と合わせて提出する必要があります。
加えて、宅建業のオフィスには、以下の法定掲示物を準備する義務もあります。
- 宅地建物取引業者票(標識)
- 報酬額表
- 取引台帳、契約書および重要事項説明書
- 従業者証明書および従業者名簿
免許取得時に加え、行政からの指導の際にも確認されるため、宅建業をレンタルオフィスで開業する際には準備漏れがないよう注意しましょう。
宅建業をレンタルオフィスで開業するメリット
宅建業をレンタルオフィスで開業するメリットは、初期費用を抑えて好立地に事務所を構えられることです。一般的な賃貸オフィスの場合、入居時には敷金・礼金や保証金、家具購入など多額の初期費用がかかります。
一方でレンタルオフィスではオフィス家具やインターネット、電話などがあらかじめ備えられているケースが多く、初期投資を大幅に削減可能です。
また、レンタルオフィスは駅前や都心の一等地に位置していることが多いため、利便性が高く、顧客を見つけやすい点も魅力です。
さらに、共有スペースを通じて異業種の経営者や個人事業主と交流する機会もあり、新しい人脈形成やビジネスチャンスを生み出すことができます。
まとめ
レンタルオフィスを使った宅建業開業には、専用の完全個室、24時間365日の利用権、接客設備を含む十分なスペース確保といった要件が求められます。また、事務所として認められるためのOA機器や固定電話、法定掲示物などの設置義務もあります。開業後にトラブルが起きないよう、契約前にはレンタルオフィス運営会社だけでなく、各都道府県の宅建業免許担当部署や専門家への事前確認が必須です。
要件を満たしたレンタルオフィスを見つけられたなら、好立地の建物で初期投資を抑えつつ宅建業を開業するチャンスになります。信頼できるレンタルオフィス事業者を探し、宅建業を開業しましょう。