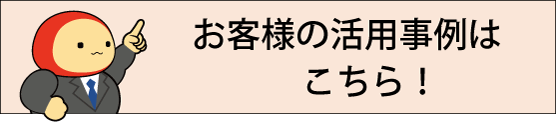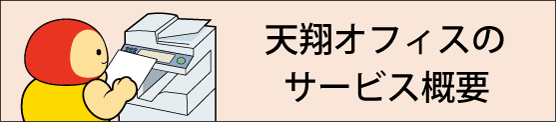安全なテレワークのためのセキュリティ対策10選と注意点を解説!
投稿日:2020年12月25日
更新日:2025年10月27日

新たにテレワークを導入することになったという企業は多いです。自宅だけでなく自由な場所で仕事ができるのは大きなメリットですが、「インターネットさえあればできる」というものでもありません。最も気を付けたいことは、セキュリティ対策についてです。安全にテレワークをするためには、どういった点に注意すればよいのでしょう。
今回は、テレワークの際のセキュリティ対策の注意点について解説します。
テレワークにおけるセキュリティ対策の必要性
テレワークをするにあたって、セキュリティ対策は必須です。万が一、機密性の高い情報が漏えいするとサイバー犯罪の被害に遭ったり、個人情報が流出すると詐欺など悪質な犯罪に巻き込まれたりする可能性があります。
また、不十分なセキュリティ対策では、会社や従業員が被害に遭うだけでなく、加害者になってしまうことも考えられます。社内で管理している顧客リストが流出する、テレワークで使用しているパソコンがウイルスに感染して社内や取引先に被害を拡大してしまう、詐欺などの犯罪に加担してしまうといった事態も起こり得ます。
以下には、特に注意しておきたい状況を挙げています。どういったリスクがあるか、注意点を確認しましょう。
業務データの持ち運び
USBなどでの業務データの持ち運びは、盗難や紛失による情報漏えいのリスクがあります。USBがウイルスに感染していると、そのUSBを使用することによってほかのパソコンにも感染を広げてしまう恐れもあります。
また、個人利用のオンラインストレージやフリーメールから情報漏えいする可能性もあるので注意しましょう。
カフェなど公共の場での業務
自宅ではなかなか集中できないと、カフェなど公共の場所で仕事を進める方もいるでしょう。しかし、不特定多数の人が集まるような場所では、直接パソコン画面をのぞき見されて情報が洩れてしまうことが考えられます。
また、オンライン会議でイヤホンをしていると、周りの音が聞こえづらい状態になっています。そういった場合、つい声が大きくなってしまい、会議の会話が周囲に聞こえてしまう可能性もあります。
公共のWi-Fiの利用にも十分に注意しなければなりません。公共Wi-Fiの中には、セキュリティが不十分なものも多いです。悪意のある詐欺Wi-Fiが含まれていることもあるため、できる限り利用しないのが一番です。
私物の端末や家庭用のネットワーク利用
会社から支給された端末ではなく、個人の私物の端末を利用する場合や、家庭用Wi-Fiなどのネットワークを使う場合にもセキュリティには注意する必要があります。個人でセキュリティ対策をする場合、個人の知識やモラルによって対策の仕方が異なるため、オフィスで使用するものよりもセキュリティが甘いことも少なくありません。
家庭用Wi-Fiのルーターのセキュリティ面に問題があった場合、第三者の不正侵入や不正サイトへの誘導の可能性があるほか、ウイルス感染のリスクもあります。
テレワークで実践すべきセキュリティ対策10選
テレワーク環境では、社外からの不正アクセスや情報漏えいなど、企業に深刻な影響を与えるリスクが高まります。安全な業務環境を維持するためには、端末やネットワーク、利用者すべてのレベルで多層的なセキュリティ対策を実施することが重要です。ここでは、テレワークで実践すべき主要なセキュリティ対策を10項目に分けて解説します。
OS・ソフトウェアのアップデート
OSやソフトウェアのアップデートは、テレワーク環境における最も基本的で重要なセキュリティ対策の1つです。更新プログラムには、既知の脆弱性を修正するセキュリティパッチが含まれており、攻撃者が不正侵入の足がかりとするリスクを防ぐ役割を果たします。アップデートを怠ると、古い脆弱性を悪用したサイバー攻撃を受ける可能性が高まるため、常に最新の状態を保つことが大切です。
OSアップデートには、新機能の追加や不具合修正、操作性の向上といった利点もあります。一方で、更新中の電源遮断や通信切断によってデータが破損する恐れがあるため、実行前にはバックアップの取得や十分な電源・通信環境の確保を行いましょう。こまめなアップデートの実施が、システムの安定性と安全性を維持する第一歩となります。
ハードディスクの暗号化
ハードディスクの暗号化は、テレワークにおける情報漏えい対策として欠かせない手段です。ノートパソコンの紛失や盗難、第三者による不正アクセスなどの際にも、データを読み取られないよう保護できます。ログインパスワードだけでは不十分なため、保存データ自体を暗号化することで安全性を高めることが重要です。
暗号化の方式には、ハードディスク全体を保護する「フルディスク暗号化」、ドライブ単位で行う「部分暗号化」、必要なファイルやフォルダだけを対象とする「個別暗号化」などがあります。導入方法としては、Windowsの「BitLocker」などの標準機能を活用するほか、専用ソフトや暗号化機能付きハードディスクを利用する方法もあります。導入前には必ずバックアップを取り、復号やトラブル対応の手順を確認しましょう。
パスワードレス認証の利用
パスワードは長年セキュリティの基本とされてきましたが、推測・流出・使い回しなどによる不正アクセスのリスクが高く、もはや万全とは言えません。そこで注目されているのが「パスワードレス認証」です。パスワードレス認証は、パスワードを使わずに本人確認を行う仕組みで、生体情報や端末情報を用いることで、なりすましや情報漏えいのリスクを大幅に低減します。
主な方式には、指紋や顔認証などの「生体認証」、スマートフォンなど本人所有のデバイスを用いる「デバイス認証」、公開鍵暗号を活用する「FIDO認証」などがあります。FIDOは国際標準規格で、サーバー側にパスワードや生体情報を保存しない仕組みのため、情報流出の懸念が小さい点が特徴です。導入時は、利用環境や運用方法を確認し、対応デバイスや認証方式を統一しましょう。
VPNサービスの利用
VPN(Virtual Private Network)は、インターネット上に仮想的な専用線を構築し、安全な通信を実現する仕組みです。通信内容が暗号化されるため、外部からの盗聴や改ざんを防ぎつつ、社内ネットワークと同等のセキュリティで業務を行えます。テレワークにおいては、自宅や外出先からでも安心して社内システムへアクセスできる点が大きな利点です。
導入することで、社内ポリシーを維持したまま安全な接続が可能となり、作業の効率化や柔軟な働き方にも貢献します。ただし、VPNに接続していない状態での通信や、VPN機器自体の脆弱性を放置することはリスクとなります。定期的なソフトウェア更新や多要素認証の導入など、VPN環境そのものの保守管理を徹底することが、安全なテレワーク運用のポイントです。
セキュリティ機能付きUSBや信頼できるクラウドサービスの利用
テレワークでは、社外でのデータ共有が増えるため、USBやクラウドサービスの安全性確保が欠かせません。USBは、暗号化機能やウイルス対策機能を備えた「セキュリティ機能付きタイプ」を利用することで、紛失や不正アクセスによる情報漏えいを防げます。利用後はデータを残さず削除し、持ち出し制限を設けましょう。
クラウドサービスを活用する場合は、セキュリティ体制が整った信頼できる事業者を選ぶことが大切です。通信の暗号化や不正アクセス防止、データバックアップ体制を確認しましょう。クラウド型セキュリティは最新の脅威情報を自動反映でき、テレワーク環境でも高い安全性を保てます。
ゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)の活用
ゼロトラストネットワークアクセス(ZTNA)は、「何も信頼しない」を前提とした新しいセキュリティモデルです。ユーザーや端末の信頼性を常に検証し、必要最小限の権限でのみアクセスを許可する仕組みを採用しています。通信はZTNAの仲介システムを経由して暗号化され、内部不正や外部侵入のリスクを大幅に軽減できます。
従来のVPNは、一度認証されると社内ネットワーク全体にアクセスできる構造でしたが、ZTNAではアプリやユーザー単位でアクセスを制御します。そのため、侵入が起きても被害を局所化できる点が大きな特徴です。クラウド環境との親和性が高く、柔軟なスケーラビリティと高い通信品質を両立します。テレワークの普及やクラウド利用拡大に伴い、脱VPNとZTNAへの移行が急速に進んでいます。
EDRによる端末監視・対応
EDR(Endpoint Detection and Response)は、端末上の挙動を常時監視し、不審な動きを検知・対応する仕組みです。従来のウイルス対策ソフト(EPP)では検出できない「ファイルレス攻撃」や未知の脅威にも対応できる点が特徴です。テレワーク環境でも、端末の挙動を遠隔から監視・隔離・修復できるため、迅速なインシデント対応が可能になります。
EDRの導入により、攻撃の早期発見や被害の最小化が期待できますが、コストや運用負荷が高くなる点に注意が必要です。製品を選定する際は、検知精度・対応OS・クラウド対応可否・サポート体制などを比較検討しましょう。クラウド型EDRを活用すれば、場所を問わず端末を一元管理でき、テレワーク時のセキュリティレベルを大幅に向上させられます。
MDM/UEMによるデバイス管理
UEM(Unified Endpoint Management)は、PC・スマートフォン・タブレットなどの端末を一元管理し、組織全体のセキュリティを強化できるツールです。従来のMDM(モバイルデバイス管理)がモバイル端末のみを対象としていたのに対し、UEMはあらゆるデバイスを包括的に管理できます。BYOD環境にも対応し、業務と個人利用のデータを分離することで、情報漏えいを防ぎつつ利便性を保てます。
導入により、設定の自動化やポリシーの一元適用が可能となり、管理コストの削減や生産性向上が期待できます。ただし、古いOSや非対応端末では利用できない場合があるため、導入前の検証が必要です。テレワーク環境でも、安全で効率的な端末管理を実現できます。
セキュリティ教育とフィッシング対策訓練
テレワーク環境では、従業員が仕事用端末でフィッシングメールに引っかかるリスクがあります。業務用のアカウントを狙った巧妙なメールも多く、誤ってリンクを開いたり情報を入力したりすると、企業データの漏えいやマルウェア感染につながる恐れがあります。
このような被害を防ぐためには、従業員へのセキュリティ教育と定期的なフィッシング対策訓練が重要です。教育では、怪しいメールの特徴や安全なパスワード管理、企業ポリシーの遵守を徹底することなどを伝えましょう。実際のフィッシングを模した訓練を行うことで、実践的な判断力を身につけられます。継続的な教育と訓練により、組織全体のセキュリティ意識を高め、リスクを最小限に抑えられます。
ログ監視とSIEM/SOARの活用
SOAR(Security Orchestration, Automation and Response)は、セキュリティ運用を自動化・効率化するためのソリューションです。サイバー攻撃などのインシデント発生時に、監視・分析から一次対応までを自動化し、担当者の負担を軽減します。複数のツールを連携させてログを収集(オーケストレーション)し、分析・判断(オートメーション)、対応実行(レスポンス)までを自動で行うのが特徴です。
一方、SIEM(Security Information and Event Management)はログの監視と相関分析を行い、潜在的な脅威を検出する仕組みです。SOARはこのSIEMと連携し、検知後の対応を自動化する役割を担います。導入により、対応スピードの向上・作業品質の均一化・人材不足の緩和などが期待できます。ただし、事前の運用設計やルール整備が不十分だと、誤検知への対応遅延が生じる恐れもあります。
公共の場でののぞき見や会話に注意
自宅だけでなく、自由な場所で仕事ができるのがテレワークの魅力の1つです。セキュリティ面が不安だということは分かっていても、自宅以外のほうが仕事が捗るという方もいるかもしれません。
公共の場で業務を進める場合には、のぞき見やオンライン会議での話し声が周囲に聞こえないように注意しましょう。見られてしまう恐れのあるような場所でパソコンを開く可能性がある場合は、のぞき見防止フィルムなどを使用する手もあります。また、のぞき見を防止できるソフトも公開されているので、これらを活用するのもおすすめです。
サテライトオフィスを活用して安全なテレワークを
セキュリティ対策がしっかりしたテレワーク環境が職場から提供されている場合は安心ですが、従業員個人の私物端末を業務に使う必要がある場合には、従業員それぞれが自身でセキュリティ対策を見直さなくてはなりません。
しかし、ITに対してあまり知識が深くない方や職場に相談できるシステム管理者がいない場合は、適切なセキュリティ対策ができてない可能性も高いです。このようにセキュリティ対策に不安がある場合には、サテライトオフィスを活用するというのも選択肢の1つです。
サテライトオフィスは、ウイルス感染や情報漏えいなどのリスク管理が行き届いているところも多く、自宅ではなかなか業務に集中しづらいという方も、より安心して業務に臨めます。
サテライトオフィスの多くは、法人だけでなく、個人がレンタルオフィスとして借りることもできます。新たにテレワークをすることになり、自宅ではセキュリティ面に不安があるという方にも、サテライトオフィスはおすすめです。