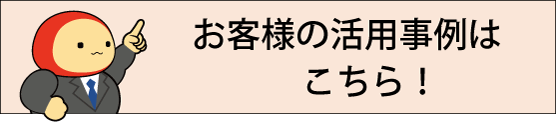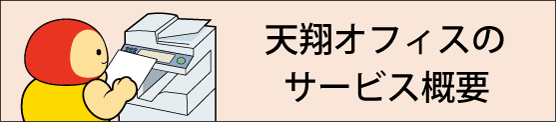酒類販売業免許はレンタルオフィスでも取得できる?販売場の要件も解説
投稿日:2025年11月28日
更新日:2025年11月28日

酒類販売免許(酒販免許)を取得するには、販売場が法律で定められた「場所的要件」を満たすことが必須です。しかし、「営業所がレンタルオフィスでも許可は下りる?」「設備は最小限で大丈夫?」など、酒類販売業の開業場所に関して悩みを抱える方は多いでしょう。
当記事では、酒類販売業免許を取得する際に販売場として満たすべき具体的な要件、レンタルオフィスを利用する際の注意点、メリット・デメリット、東京で利用しやすいレンタルオフィスを説明します。
目次
酒類販売業免許はレンタルオフィスでも取得できる?
酒類販売業免許は、一定の条件を満たせばレンタルオフィスでも取得できる可能性があります。酒類販売業免許は「特定の販売場」に対して付与されるため、申請時には事務所として機能する実在のスペースが必要です。たとえば、専用の個室を確保でき、販売場として適切に管理できるレンタルオフィスであれば申請は可能です。
酒類販売業では許可取得は可能
酒類販売業免許は「販売場」として指定した実在の場所に与えられるため、申請時には業務を行うための事務所や営業所が必要となります。この点で、住所のみを提供するバーチャルオフィスは販売場として認められず、申請することはできません。
一方、レンタルオフィスでも鍵付きの個室や固定席のように、継続的に使用できる明確なスペースが確保されていれば、販売場として扱われる場合があります。ただし、フリーアドレス型の席や共有スペースのみの契約は、業務実態が特定できないため許可の対象外です。
酒類販売業の販売場の要件
酒類販売業の免許申請では、複数の要件を満たす必要があります。その中の1つが「場所的要件」です。税務署の手引では、販売場が取り締まり上不適当と認められる場所でないことが求められているため、具体的な基準を踏まえて申請する必要があります。
2 酒税法10条9号関係の要件(場所的要件)
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと
(引用:税務署「一般酒類小売業免許申請の手引」/ https://www.nta.go.jp/taxes/sake/menkyo/tebiki/01.pdf 引用日2025/11/05)
ここでは、酒類販売業免許申請における場所的要件を満たす基準のポイントを解説します。
ほかの飲食店に隣接していないか
販売場が居酒屋や飲食店に隣接している場合、酒類販売業免許は基本的に認められません。これは、飲食用のお酒と販売用のお酒が混在し、在庫管理が不適切になる恐れがあるためです。販売場は、事業として独立したスペースであることが必要とされます。
ただし、隣接している場合でも、飲食スペースと販売場の独立性が明確に確保されていれば、例外的に認められるケースもあります。たとえば、販売場に専用の入り口を設ける、鍵付きドアで完全に区画する、パーテーションで明確にスペースを分けるなど、ほかのテナントや飲食スペースと混ざらない構造にすることが重要です。陳列棚を販売場側だけに設置したり、試飲カウンターやイートインスペースを排除したりする形で申請する方法もあります。
ほかの酒類販売業者と同じ場所ではないか
酒類販売業免許は、すでにほかの酒類販売業者が同じ場所で免許を取得している場合、その場所を販売場として再度申請することはできません。複数の事業者が同一スペースを使用すると、お酒の在庫が混在し、どの事業者の商品であるか判別できなくなるため、適切な管理が行えないと判断されるためです。
ただし、同じ建物内であっても、各事業者のスペースが明確に区画され、商品の陳列棚やレジが独立して設けられている場合は例外的に認められるケースがあります。大型商業施設内に複数の酒類販売店が存在しているのは、それぞれが専用の売り場と決済場所を持ち、従業員も独立しているためです。一方で、他店の一部の棚を間借りし、共通のレジで決済する形態は、区分が不十分とみなされ、販売場として認められません。
適正な使用権限がある場所か
酒類販売業免許を取得するためには、申請者がその場所を正当に使用できる「適正な使用権限」を持っていることが必須です。これは、土地や建物の所有者から、申請するスペースで酒類販売業を行うことを明確に許可されているかどうかを示すものです。
具体的には、不動産登記簿や賃貸借契約書の提出により、使用権限を証明することが求められます。ただし、転貸借のように所有者と貸主が異なる場合や、契約内容に酒類販売の実施が含まれていない場合は、所有者から追加で「使用承諾書」を取得しなければなりません。レンタルオフィスでも同様で、運営会社だけでなく建物所有者の承諾が必要となるケースがあります。
レンタルオフィスで酒類販売業を営業するメリット・デメリット
レンタルオフィスは、初期費用を抑えつつ事務所機能を確保できるため、酒類販売業を始めたい方にとって検討しやすい選択肢の1つです。ただし、販売場として認められるには条件があり、物件によって免許取得の可否が分かれる点には注意が必要です。ここでは、レンタルオフィスを利用する際のメリットとデメリットを説明します。
メリット
レンタルオフィスは、酒類販売業を起業する際の負担を軽減し、事業を立ち上げやすくする点で多くのメリットがあります。主なメリットは下記の通りです。
- 初期費用を抑えられる
通常の賃貸オフィスでは敷金・礼金・仲介手数料などが必要になり、契約時に高額な負担が発生します。一方、レンタルオフィスは契約金や保証金のみで契約できる場合が多く、家具やインターネット環境も整っているため、初期費用を大幅に削減できます。 - 交通の便がよい
都心部や主要駅の近くにオフィスを構えることができるため、仕入れや打ち合わせの移動がスムーズになります。アクセスのよさは、事業の信頼性向上や商談機会の拡大にもつながります。 - 柔軟な契約ができる
レンタルオフィスは短期契約に対応しており、事業の成長に合わせてスペースの拡張や縮小がしやすい点が魅力です。長期の賃貸契約に縛られず、必要な期間だけ利用できるため、リスクを抑えて酒類販売業をスタートできます。
デメリット
レンタルオフィスは便利な一方で、酒類販売業の申請では注意点もあります。
- レンタルオフィスによっては許可を取得できない
酒類販売業免許を取るには、レンタルオフィスが独立した販売場として認められる必要があります。鍵付きの個室であれば申請可能な場合がありますが、フリーアドレス型のようにスペースが固定されていないタイプは販売場として認められません。また、半個室タイプも構造によって判断が分かれます。 - 物件所有者の承諾が必要となる
レンタルオフィスは貸主と所有者が異なるケースが多く、契約書だけでは使用権限が証明できない場合があります。そのため、酒類販売業を行うことについて建物所有者から「使用承諾書」を得る必要があります。転貸借構造の場合は手続きが複雑になることも多く、許可取得のハードルは上がりやすくなります。
東京で酒類販売業を開業するならTENSHOOFFICEの利用がおすすめ
東京都内で酒類販売業の開業を考えている場合は、TENSHOOFFICEのレンタルオフィスをぜひご利用ください。TENSHOOFFICEはすべて都心一等地に位置し、法人登記が可能な完全個室をご提供しているため、酒類販売業の「営業所」として必要な環境を整えやすい点が特徴です。
また、会議室やフリースペースなどの設備は無料で利用でき、オフィス家具・インターネットも即日利用できます。1名~10名以上まで柔軟にお部屋を選べるため、事業の成長に合わせたオフィス運用が可能です。まずは一度ご相談ください。
まとめ
酒類販売業を営む際は、販売場が場所的要件に適合しているかどうかが重要となります。ほかの販売業者と同一場所でないこと、適正な使用権限があること、業務に必要な設備を備えた独立性のある空間であることは、いずれも満たすべき要件です。こうした要件を踏まえた上で、事業をスムーズに進めるためには、開業しやすい環境が整ったオフィスを選ぶことが大切です。
東京都内にあるTENSHOOFFICEは、立地・設備・コストのバランスに優れたレンタルオフィスです。必要な条件を満たしながら負担を抑えて準備を進められますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。