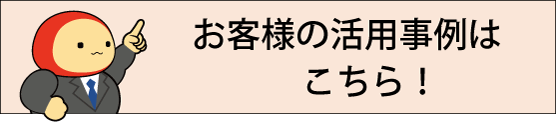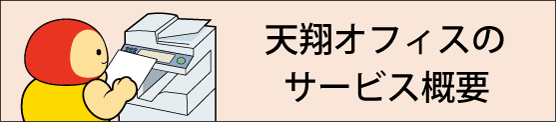古物商はレンタルオフィスで開業できる?必要な営業所の条件も解説
投稿日:2025年10月27日
更新日:2025年10月27日

古物商許可証を取得したいものの、「事業所に自宅住所は使いたくない」「賃貸オフィスは高い」と、開業場所に迷う方は少なくありません。特に東京都心での開業を考える場合、コストと許可要件のバランスは大きな壁になります。そのため、レンタルオフィスの利用を検討する方もいるでしょう。
当記事では、レンタルオフィスが許可の対象になる条件、営業所に求められる3つの要件、レンタルオフィスを選ぶ際のメリット・デメリット、東京で開業する方に適したレンタルオフィスを紹介します。自分の計画に適したオフィスが判断できれば、安心して申請準備に進めるでしょう。
目次
古物商許可はレンタルオフィスで取得できる?
レンタルオフィスでも古物商の許認可を取得できる可能性はありますが、どのような構造や契約形態のオフィスであるかによって判断が分かれます。古物商許可の審査では、事務所・営業所として独立して管理できる実態が求められるため、簡易なパーテーションで区切られただけの共有スペースでは不許可となるケースが多く見られます。一方で、施錠可能な個室型のレンタルオフィスであれば、営業所としての独立性を満たしやすく、許可取得の可能性が高まります。
また、「使用権限」が継続的に認められる契約形態であることも重要な条件です。デイリー利用や短期契約ではなく、中長期的な占有契約であるかどうか、さらに古物営業の用途での利用について運営会社から承諾を得られるかといった点も審査対象となります。つまり、レンタルオフィスだから不可というわけではなく、条件を満たす形態・契約内容であれば取得は現実的に可能と言えるでしょう。
バーチャルオフィスでは許可取得は不可能
バーチャルオフィスを営業所として古物商許可を取得することはできません。その理由は、バーチャルオフィスは住所のみを貸し出すサービスであり、実際に事業者などの人が常駐する「営業所としての実態」が存在しないためです。古物商許可では「営業所が実在し、独立して管理できる場所であること」が前提条件とされており、バーチャルオフィスはこの条件を満たしません。
中には「形式上は住所があるからよいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、取引トラブルなどが発生した際に警察や取引先がバーチャルオフィスを訪問しても営業所自体は存在せず、「どこに会社があって誰が担当者なのか」をすぐに判断できないことから営業所とは認められません。実際、現場で人の出入りがないバーチャルオフィスでは、申請段階で受理されないケースがほとんどです。そのため、古物商許可を前提に開業を検討する場合、バーチャルオフィスの利用は選択肢に入らないと考えるべきと言えるでしょう。
古物商の営業所の条件
古物商許可を取得するには、まず営業所が法律上の基準を満たしている必要があります。ここでは、審査で重視される「独立性」「実態性」「使用権限」の3つの観点から、営業所として求められる主な条件を分かりやすく解説します。
営業所として独立して管理できること
古物商の営業所として認められるのは、外形上も実態としても「独立して管理できる区画」がある場所です。つまり、他者と空間を共有せず、壁などで区切られた専有空間が必要です。これは、古物営業法に則った古物商プレート(標識)の掲示や古物台帳の保管を行う必要があるほか、第三者の個人から見ても営業所として識別できる状態が求められるためです。
たとえば、自宅を営業所とする場合、複数人が同住所で申請して外見上区別できないと独立性を欠くと判断されることがあります。また、シェアオフィスやコワーキングスペースなどのオープンな席利用は独立性が認められませんが、個室型で専用占有が担保されていれば認められる可能性があります。
営業所としての実態があること
古物商の営業所は、単に住所があるだけでは足りず、実際に古物営業が行われていると外部から確認できる「営業実態」が必要です。具体的には、営業所ごとに常勤の管理者がいて日常的に業務を行っていること、古物の保管スペースが確保されていること、古物台帳を法に従って記録・保存できる環境が整っていることが求められます。
さらに、入口などの見やすい場所に古物商プレートを掲示し、営業内容が対外的に明示されていることも義務です。これらの義務を履行できないバーチャルオフィスのような実態を伴わない場所は、営業所とは認められません。
営業所としての使用権限があること
古物商の営業所として認められるには、その場所を中長期的に使用できる「権限」が必要です。自己所有物件であれば当然この条件を満たしますが、賃貸物件を利用する場合は契約上、その用途が許可されているかが問題になります。
特に、住居用賃貸では用途制限により古物営業などの商業利用に使えないケースもあるため、大家や管理会社からの承諾、場合によっては使用承諾書の取得が必要です。また、古物商許可申請時は使用権限に関する書類の提出が原則不要とされますが、一部地域では例外的に求められることがあります。どの物件でも営業に使ってよいわけではないため、契約内容・承諾状況・利用期間を事前に確認し、継続利用の裏付けを備えることが重要です。
レンタルオフィスで古物商を営業するメリット・デメリット
レンタルオフィスを営業所として古物商を開業する場合、初期費用を抑えられる一方で、申請要件との相性や運用面での制約が生じることがあります。ここでは、古物商という業態の視点から見たレンタルオフィス利用のメリット・デメリットを整理します。
メリット
レンタルオフィスを古物商の営業所として活用する最大の利点は、初期コストと準備工数を大きく削減できる点です。一般的な賃貸オフィスでは敷金・保証金などで約10~12か月分の資金を要することもありますが、レンタルオフィスなら約1~3か月分の敷金で契約でき、資金を仕入や運転資金に回せます。
さらに、家具・ネット環境・電気などがすでに整備されているため、契約後すぐに営業を開始でき、古物台帳の管理場所や商談スペースも確保しやすい環境です。有人受付や宅配受取、電話代行などの付帯サービスを活用すれば、買取商品の受領対応や顧客対応の工数を外部化でき、本業に集中できるでしょう。
デメリット
レンタルオフィスは初期負担の支払いが少ない一方で、坪単価は通常の賃貸より高めに設定されているため、長期運用では総コストが膨らむ可能性があります。会議室利用や宅配・電話対応などのオプションを多用すると、追加費用が重なることで割高に感じられるかもしれません。
また、レンタルスペースは小規模な場合が多いため、扱う古物や中古品が増えた際に保管場所の確保が難しくなる恐れがあります。レンタルオフィスでは自由に内装の変更ができず、防犯設備や棚の増設など、古物商業者特有の運用ニーズに制約がかかる点にも注意が必要です。
東京で古物商を開業するならTENSHOOFFICEの利用がおすすめ
TENSHOOFFICEのレンタルオフィスは、すべての拠点が東京都心のビジネス街に位置し、駅から徒歩約5分以内の一等地で法人登記が可能です。完全個室や施錠可能なブースタイプをご用意しており、古物商許可で求められる「独立性」の確保にも適しています。会議室やフリースペースを無料で利用でき、宅配ボックスや専用ポスト、オートロックなどの設備も充実しております。
初期費用は契約金と初月賃料・共益費のみ、水道光熱費・更新料・原状回復費も不要で、イニシャルとランニングの両面でコストを抑えられます。規模拡大や拠点移動にも柔軟に対応しているため、安定した運用と将来の展開を見据えた拠点としてぜひご活用ください。
まとめ
古物商として開業する場合、営業所は「独立して管理できる実体があり」「中長期的に使用できる権限を有している場所」でなければならず、バーチャルオフィスでは許可取得は認められません。一方で、個室型のレンタルオフィスで構造や契約、承諾などの条件が整っていれば、古物商許可を取得して営業することは十分に可能です。
レンタルオフィスを利用すれば、初期費用を抑えて都市部に拠点を構えられます。東京で開業を検討している場合は、古物商の営業所条件を満たしやすく、コストパフォーマンスの高いTENSHOOFFICEを候補に入れ、比較検討してみてください。