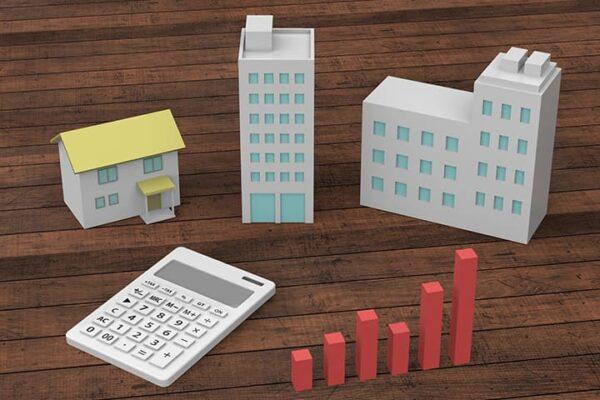クリニック開業の基礎知識一覧
-
クリニックの開業に必要な資金はいくら?内訳や診療科別の目安を解説
 クリニック開業の基礎知識 2025/09/18
クリニック開業の基礎知識 2025/09/18クリニックを開業する際に気になるのが「どのくらいの資金が必要か」という点でしょう。一般的に開業には数千万円規模の費用がかかり、診療科目や診療範囲によって必要額は大きく変動します。融資を受けるだけでなく、総資金の1~2割程度の自己資金を用意しておくと、資金調達や開業後の経営安定にも有利です。 当記事では、クリニック開業に必要な自己資金や資金内訳を整理した上で、診療科別の開業資金の目安を詳しく解説します。開業を検討している方は、自院の計画にあわせた資金計画を立てる参考にしてください。 クリニック開業に必要な自己資金 クリニックを開業する際には、金融機関から融資を受けることが一般的ですが、自己資金も一定額を準備しておくことが望ましいとされています。開業の規模や診療科目によって必要額は変動しますが、一般的には総開業資金の1~2割程度を目安に考えると安心です。たとえば、クリニックの開業資金は5,000万~1億円程度とされており、その場合は500万~2,000万円程度の自己資金が目安となります。 自己資金を確保しておくことで融資審査を有利に進められるほか、開業後の資金繰りの安定にもつながります。自己資金が少ないからといって開業が不可能になるわけではありませんが、開業を現実的に進める上で準備しておくことが望ましいでしょう。 開業に必要な資金の内訳 クリニック開業に必要な資金は、規模や診療科目によって大きく変動しますが、主な費用項目は共通しています。まず土地や建物にかかる不動産費用、仲介会社への手数料、患者層に合わせた内装工事費があります。次に、診療に不可欠な医療機器や什器の購入費、スタッフ採用や広告宣伝のための費用も必要です。さらに、開業直後は患者数が安定しないため、一定期間の人件費や家賃・光熱費を賄う運転資金も確保しておかなければなりません。 費用項目概要不動産費用購入・賃貸、敷金・礼金など内装工事費診療科目に適した内装整備医療機器・什器検査機器や電子カルテ等採用・人件費医師以外のスタッフ確保広告宣伝費チラシやWEB広告等運転資金開業後の固定費を賄う資金 【診療科別】クリニックの開業資金の目安 診療科開業資金の目安金額内科約6,000万~8,000万円整形外科約6,000万~9,000万円眼科約5,000万~7,500万円耳鼻咽喉科約5,000万~8,000万円皮膚科約2,000万~6,000万円小児科約4,000万~6,000万円精神科・心療内科約1,500万~3,000万円産科・婦人科約5,000万~6,000万円 クリニック開業に必要な資金は、診療科目によって大きく異なります。一般的には数千万円規模が必要であり、たとえば整形外科や内科では約6,000万~9,000万円かかります。一方、精神科や心療内科は約1,500万~3,000万円と比較的低い水準での開業も可能です。 診療科ごとに必要な医療機器や設備が異なるため、このように大きな差が生じます。以下では、各診療科別に開業資金の目安を解説します。 内科 内科の開業資金は約6,000万~8,000万円が目安とされています。自己資金は約600万~1,600万円ほど準備できると安心でしょう。内科は一般内科だけでなく、消化器内科や循環器内科など専門領域によって必要な設備が大きく異なります。 たとえば、消化器内科では上下内視鏡に対応するため検査室や回復室、複数のトイレ設置が必要になり、設備投資額が増える傾向にあります。循環器内科や呼吸器内科も専門性の高い医療機器が必須となるため、一般内科に比べて費用が高くなるケースがあります。開業を検討する際は、診療科の専門性や導入機器の範囲を明確にし、資金計画を立てましょう。 整形外科 整形外科の開業資金は約6,000万~9,000万円が目安で、自己資金は約600万~1,800万円ほどあるのが望ましいです。整形外科クリニックは一般診療に加え、リハビリテーションを行うための広いスペースや設備が必要になります。X線撮影装置や骨密度測定装置などの検査機器に加え、リハビリ機器やベッドの導入が必須となるため、他の診療科目よりも初期費用が高くなりがちです。 理学療法士や作業療法士など専門スタッフの雇用も欠かせないため、人件費も比較的高額になります。開業規模やリハビリ設備の充実度をどこまで求めるかによって資金計画は大きく変わるため、導入する機器や人員を慎重に検討しましょう。 眼科 眼科の開業資金は約5,000万~7,500万円が目安で、自己資金は約500万~1,500万円が目安です。眼科は診療範囲によって必要な費用が大きく変わるのが特徴です。白内障手術やレーザー治療を行う場合は、手術室の整備や専用医療機器の導入が必要となり、追加で数千万円の投資が発生することもあります。一方で、手術を行わない外来中心の診療であれば比較的費用を抑えられます。 若い世代をターゲットとする場合には、コンタクトレンズ検査用の診断機器が必須となるため、患者層や地域の需要に応じた診療範囲の設定が重要です。地域特性を踏まえた投資計画を立てることで、資金の使い方に無駄がなくなり、安定した経営につながるでしょう。 耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科の開業資金は約5,000万~8,000万円が目安で、自己資金は約500万~1,600万円ほど確保しておくのが望ましいでしょう。診療に必要なユニットや各種検査機器に加え、聴力検査のための防音室を設置する必要があるため、ほかの診療科に比べて建物工事費が高くなる傾向があります。 また、患者への説明を分かりやすくするため、カメラやモニターを導入しているクリニックも多く見られます。さらに、手術対応の有無によって導入すべき機器や必要スペースが大きく変わるため、開業計画段階で診療内容を明確にしておくことが大切です。地域の患者層や診療方針を踏まえた設備投資を行うことで、資金を有効に活用でき、安定した経営につながるでしょう。 皮膚科 皮膚科の開業資金は約2,000万~6,000万円程度が目安とされています。自己資金としては200万~1,200万円程度を用意できるとよいでしょう。皮膚科は高額な検査機器や広い敷地を必要としないため、比較的低コストで開業できる診療科です。 その一方で、美容皮膚科を取り入れる場合は、レーザー治療機器など高額な設備投資が必要となるため、開業資金は大きく増える傾向があります。診療内容やターゲット患者層をどう設定するかによって資金規模が大きく変わる点が特徴です。 小児科 小児科の開業資金は約4,000万~6,000万円が目安で、自己資金としては約400万~1,200万円ほどを準備しておくと安心です。小児科は高額な医療機器を必要としないケースが多いため、資金の多くは建物や内装に充てられます。特に感染症対策として隔離室や専用動線を確保することが重要であり、安心して受診できる環境づくりが求められます。 また、小児科は保護者同伴の来院が基本となるため、待合室を広めに設け、キッズスペースや授乳室、ベビーカー置き場を整備するケースも少なくありません。こうした設備を整えることで保護者からの信頼を得やすくなり、集患にもつながります。地域のニーズを踏まえた設計が、開業後の安定経営を支えるポイントです。 精神科・心療内科 精神科・心療内科の開業資金は約1,500万~3,000万円程度で、自己資金は150万~600万円が目安です。ほかの診療科と比べて必要な資金が少ないのが特徴で、理由は高額な医療機器や大規模な検査室が不要なためです。診察室や待合室を中心に構成できるため、比較的コンパクトな物件でも開業が可能です。 目立たない立地の方が好まれるケースもあり、不動産費用も抑えやすい傾向にあります。看護師配置が必須ではない点も人件費削減につながります。一方で、患者が落ち着ける空間づくりやプライバシーに配慮した内装は欠かせません。シンプルながら安心感を重視した設計が、患者からの信頼と継続的な通院につながります。 産科・婦人科 産科・婦人科の開業資金は約5,000万~6,000万円が目安ですが、これは「分娩なし」の場合です。自己資金としては約500万~1,200万円を見込むとよいでしょう。もし分娩に対応する場合は病床や分娩設備が必要になり、8,000万~1億円近くかかるケースもあります。 また、不妊治療を行う場合には、高度な生殖補助医療に必要な医療機器の導入が不可欠であり、費用が大きく上振れする要因となります。診療範囲が広がれば設備投資も比例して増えるため、開業前に明確なコンセプトを定めましょう。患者に安心感を与えるためには、施設面だけでなく、クリニックの強みを発信する取り組みも必要になります。 まとめ クリニックの開業資金は診療科目や診療範囲によって大きく異なり、精神科では約1,500万~3,000万円ですが、整形外科や内科では約6,000万~9,000万円と幅があります。一般的に総開業資金の1~2割程度の自己資金を準備しておくと融資審査や開業後の経営安定に有利です。必要な設備や内装、スタッフ体制、地域の患者ニーズを踏まえた資金計画を立てることが、クリニック開業を成功させるためのポイントとなります。 TENSHOOFFICEなら敷金2か月、礼金・更新料なし、工事期間+3か月間フリーレントと好条件で利用でき、初期費用を大幅に削減できます。東京でクリニック開業に向けて物件をお探しの方は、ぜひ気軽にご相談ください。 お問い合わせはこちらから|天翔オフィス
続きを読む -
クリニックをビルテナントで開業するメリット・デメリットとは?
 クリニック開業の基礎知識 2025/09/18
クリニック開業の基礎知識 2025/09/18クリニックの開業を目指す際は、どの形態のテナントを選ぶかによって事業の方向性が左右されます。都市部で利便性を重視する場合はビルテナント、複数科が連携する場合は医療モール、自由度の高い空間設計や地域密着を望むなら一戸建てが候補です。開業医にとっては、資金計画や患者層の特徴、将来的な運営スタイルを見据えた形態選びが欠かせません。 当記事では、それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理し、クリニック経営の実情に即した選択のヒントを提示します。クリニックの開業を目指している方はぜひ参考にしてください。 クリニックの開業形態は主に3つ クリニックの開業形態は大きく分けて、ビルテナント、医療モール、一戸建ての3種類がありますが、それぞれの特性を理解し、開業計画に合った形態を検討することが大切です。 ここでは、それぞれの形態について解説します。 ビルテナント ビルテナントでの開業は、都市部の駅前や商業エリアなど、人通りの多い場所に位置するケースが多く、認知度を高めやすい特徴があります。物件は賃貸契約で利用することが一般的で、立地条件に合わせた形で選択が可能です。 商業施設やオフィスビルの一角に開業する場合は、通勤や買い物など日常の動線に組み込まれることが多く、幅広い患者層に来院の機会を提供できます。都市部での診療ニーズに対応しやすい開業形態の1つと言えるでしょう。 医療モール 医療モールは、1つの建物や敷地内に複数の診療科が集まる形式を指します。各クリニックが近接して運営されるため、患者にとっては一度の来院で複数の医療機関にアクセスできる利便性があります。さらに、ショッピングモールや住宅地に隣接するタイプでは、生活圏と診療を結びつけやすい点が特徴です。 規模や形態はさまざまで、医療専用ビル型や複合施設型など地域特性に応じて展開されており、近年注目される開業スタイルです。 一戸建て 一戸建てでの開業は、土地を取得または所有して建物を構える形態です。外観や設計を自由に決定できるため、院内の動線や診療方針に合わせた空間を実現できます。郊外の住宅街では広い敷地を活用できるケースが多く、敷地全体を計画的に利用できる点が特徴です。 また、自宅併設型として運営する事例もあり、生活と診療を同じ場所で営むスタイルも見られます。地域社会に根付いた診療を展開しやすい開業方法です。 クリニックをビルテナントで開業するメリット ビルテナントでの開業は、都市部や駅前といった利便性の高い立地を選びやすく、初めての開業を目指す医師にも取り組みやすい点が特徴です。ここでは、ビルテナントにクリニックを構えるメリットを紹介します。 初期投資を抑えやすい ビルテナントでの開業は、不動産を購入する必要がなく賃貸契約で始められるため、初期投資を抑えられる点が特徴です。新築一戸建てでの開業と比較すると、建物建設や土地取得といった高額な資金が不要なため、開業準備に必要な資金計画を柔軟に立てやすくなります。 特に初めて開業する医師にとって、金融機関からの融資や自己資金の確保は課題となりますが、テナント開業であれば資金調達のハードルを下げられます。さらに、余剰資金を内装や医療機器の充実に振り分けることで、患者に提供する医療サービスの質を高めやすい点もメリットです。 外壁や共用部を維持管理する必要がない テナント物件では、建物全体の外壁修繕や共用部の清掃、設備管理などは原則としてオーナーや管理会社が行います。そのため、クリニック経営者自身が大規模な修繕計画や高額な工事費用を負担する必要はほとんどありません。日常的な診療業務に集中できる環境が整い、経営上の予測不能な出費リスクを抑制することにもつながります。 アクセスのよい立地で開業しやすい ビルテナントは、駅前や大型商業施設内など交通利便性の高い立地に多く存在します。そのため、患者が通院しやすく、診療科目によっては幅広い層の集患を期待できます。特に都市部では、徒歩や公共交通機関でのアクセスの良さは重要です。 また、視認性の高い場所にあることで、新規開業でも早い段階から地域住民に認知されやすい点もメリットです。立地条件を最大限に活用することで、開業初期から安定した診療体制の構築を目指せます。 クリニックをビルテナントで開業するデメリット ビルテナントでの開業は、利便性や初期投資の面で魅力的ですが、契約条件や建物の仕様によって制約が発生する点もあります。開業を検討する際には、制約やデメリットを理解しておきましょう。 内装や設備に制限がかかるケースもある ビルテナントで開業する場合、物件の構造や契約条件によって内装や設備に制限が生じることがあります。また、電気容量や給排水の条件が医療用途に適さない場合、追加工事が必要になる可能性もあります。 共用部分の改修はオーナーの許可が必要であり、診療動線やレイアウトに影響が出る場合もあります。契約前に物件の図面や設備仕様を確認し、必要な機器が問題なく稼働できるかを入念にチェックすることが欠かせません。 外観を変更するのは難しい テナント開業では、建物全体のデザインや景観を損なわないようにするため、外観の変更が制限されることが多くあります。看板の設置や広告掲示に規制がある場合、周囲への認知を十分に高められない恐れもあります。また、外壁塗装や外装工事といった改修は原則オーナーの管理下にあるため、開業者が自由に手を加えることは困難です。 契約書における広告や表示に関する取り決めは、開業前に必ず確認しておきましょう。 ランニングコストがかかる ビルテナントでは、賃料のほかに共益費や管理費が継続的に発生するので、毎月の固定費は自己所有物件に比べて高くなる傾向があります。さらに、賃料は契約更新時に値上げされる可能性があり、長期的なコスト計画を圧迫する要因となります。資産として建物が残らない点も踏まえると、毎月の支払いは経営に直結する大きな負担です。 テナント開業を選択する際は、初期投資だけでなく長期的なランニングコストを見据えた資金計画を立てることが欠かせません。 東京でクリニックを開業するならTENSHOOFFICEの利用がおすすめ 東京でクリニックを開業する際には、初期費用の負担をできるだけ軽減したいと考える方も多いでしょう。 TENSHOOFFICEでは、敷金が2か月と比較的少なく、礼金や更新料も不要です。さらに、工事期間に加えて3か月間のフリーレントが付与されるため、開業準備から診療開始まで余裕を持って計画できます。 東京都心部で利便性の高い立地を選びながら、コストを抑えてクリニックを開設するなら、TENSHOOFFICEの物件をぜひご検討ください。 まとめ クリニックの開業形態には、利便性を優先するビルテナント、診療科が連携しやすい医療モール、地域に根差した一戸建てといった選択肢があります。 ビルテナントは初期投資を抑えやすい反面、外観や内装に制約が生じることもあります。医療モールは患者にとって便利ですが、競合とのバランスを見極める必要があります。一戸建ては自由度が高い一方で資金面の負担が大きくなります。どの形態にも長所と課題があるため、開業地域の特性や医師自身の診療方針を踏まえて検討しましょう。 中には、東京のような都市部でも、初期費用を抑えながら利便性の高い立地を確保できる物件も存在します。TENSHOOFFICEは敷金2か月、礼金・更新料不要、さらに工事期間に加えて3か月間のフリーレントが用意されており、初期費用を大きく軽減できます。都市部で安定したスタートを切るための選択肢として、TENSHOOFFICEの物件をぜひご検討ください。
続きを読む